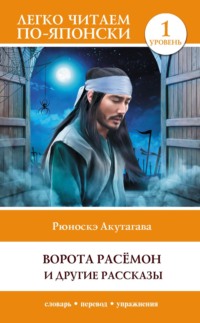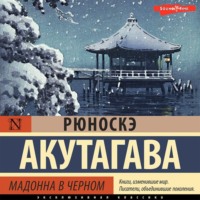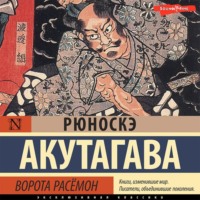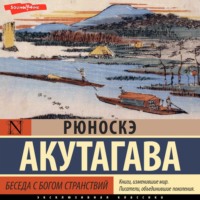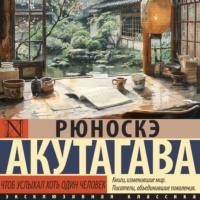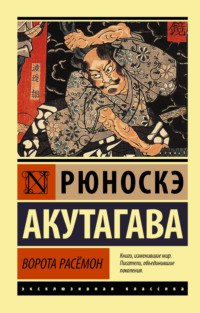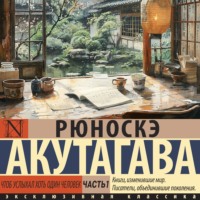羅生門 他 / Ворота Расемон и другие рассказы. Книга для чтения на японском языке

Полная версия
羅生門 他 / Ворота Расемон и другие рассказы. Книга для чтения на японском языке
Жанр: классическая прозалитература 20 векаэкранизациисборник рассказовяпонский языкяпонская литератураначало XX века
Язык: ja
Год издания: 1915
Добавлена:
Серия «近現代文学»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конец ознакомительного фрагмента
Купить и скачать всю книгу